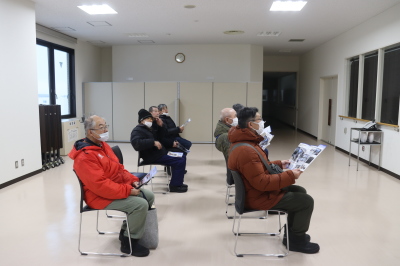令和7年1月19日 日曜日(13:00から15:00)まで、函館市消防本部において、第2回非常通信ボランティアの研修会を実施しました。
日頃、常に危機管理と向き合っている消防を訪問することによって、万が一への備え、心構え、機器の保守などについて研修を深めることができました。
研修会は、2部構成で行われました。第1部は、通信指令室の見学、第2部は、消防車両の見学でした。
通信指令室は消防本部の4階にあり、常時6名(災害時には増員)で管内の119番の受付をしています。個人情報保護から窓越しの見学となりましたが、表示板により見学時も救急車は4台出動中、また、119番が入ると、回線にランプが着くなどの様子が分かりました。
無線関係では、山間部もあることから、合併された地域には、中継局を置き。不感地帯をなくしているということでした。また、隣接する消防とも共通波でいつでも無線通信ができるようになっているということです。119番通信訓練ということで、窓の外から参加者のスマホから実際に119番をすると、目の前の受令台の職員が目の前で応答対応すると共に、ディスプレーには自分たちのいる消防本部の場所が瞬時に表示されました。かなりの精度で、位置特定はできるということでした。一方、一般加入回線においても、すぐに発信元の住所が表示されるということでした。ケータイからも固定電話からも現場の特定はすぐに特定できることがわかりました。また、すぐに切れたり、間違ってかけてしまった場合には、最悪の状況も考えた対応をしているということですので、間違えた場合は、その旨を一言言ってほしいということもお話されていました。
第2部は、消防車両の見学。所狭しと、大型消防車両が車庫で待機していました。最初に見たのは水難救助車。後ろの扉を開けると、潜水のウェアや空気ボンベが並んでいました。屋根にはボートも積んでいました。出動は、多くはないそうですが、厳寒の海でも作業するということで、実際の現場よりも訓練の方がより厳しいというお話をされていました。続いては、タンク車。2000リットルの水を積んで、火災現場へ出かけます。放水すると数分でその水は使い切ってしまうそうで、消火栓、河川などから、水を供給して、放水するそうです。最後はレスキュー車。人命を救助するための車両です。全ての火災現場に出動するそうです。車両の前後のウィンチ、車両後部のクレーン、特殊チェーンソー、エンジンカッター、ロープ、送風機など、救助に使う可能性のあるあらゆるものが積載されています。交通事故などで、内部に人が挟まれた場合などのカッター、スプレッダーという車両内空間を空ける道具など、最近の交通事故などでも使われたというお話でした。
普段は、テレビなどでは見かける映像ではありますが、生の通信指令室を見学し、また、現場の消防隊員から話を聞くということで、とても有意義な研修会になりました。
非常通信ボランティアとしても、道具(私たちで言うと無線機やアンテナ、電源)は、いつでもすぐに使えるようにしていくこと、情報は共有して、確実に伝えること、チームとして協力して作業に臨むことなど、多くの示唆をいただいた研修会となりました。
ご多用中にも対応いただいた函館市消防本部職員の皆様、そして、参加された非常通信ボランティアの皆様、ありがとうございました。

旗の左座っているJA8EJK
立っているのは左からJK8XBR,JA8VKV,JH8CBH,.JH8NNW,JM8UUY,JG8QYH,JI8PLY,JA8FSB,JM8OTS